環境の与え方が行動を制御する
今日もアクセスいただき、本当にありがとうございます。
寅丸塾の管理人です。
最近の記事はやや専門家向けの内容になってしまってますが、
難しいことを平たい言葉で表現するのは難しいですね…
前回は、
視覚と体性感覚を一致させる課題を提供することで、力任せな動きから効率的な動きにシフトする戦略方について述べていきました。
そのためには、
患者さん自身が自分の手や足に注意を向けたりセラピストの言葉から予測したりと、患者さんが主体的に治療に参加する努力も必要になります。
しかし、
臨床の現場では自分の手足に集中できない、認知的(知的)な問題を抱え、言葉のやりとり自体ができない場合も少なくありません。
私が現在勤務する療育センターでは、言葉のキャッチボールができる入所者はほんの一部のみですので、
認知運動療法士泣かせの現場と言ってよい環境です…

言葉が通用しないという問題
最近診た高齢患者さんの話です。
・転倒して大腿骨骨折、以降はほぼ寝たきり生活
・身体が丸まって(円背)固まり、自分の背中や足に手が届かない
・車椅子に乗せても自分の力で身体を支えられないのでクッションを詰め込んで何とか支えている(奉られている?)
・足は全く役に立っておらず、「宙ぶらりん」な状態
・知的な問題のため会話は殆どできないが、愛想はよくセラピストに興味を示す

こんな患者さん、医療従事者なら一度は見たことありませんか?
骨折する前はそれなりに立ったり歩いたりしていたらしいので、
足の筋力さえ戻れば自分の力で立つことが出来るだろう。
入院先のセラピストはそう考えました(多分)。
「よし、離床して立たせよう」
こうして足を使わせようとした結果、何も解決しなかった(むしろ苦痛が増えて閉じこもった)ようです。
このようなケースの場合、
外から見た世界(=外部観察)の問題は数え始めればキリがなく、「筋力」とか「関節の可動域」とか「車椅子の形」とか、矯正するターゲットを探していくのですが、中々上手くいかないことが多いです。
では、
中から見た世界(=内部観察)に目を向けてみるとどうか?
・骨折というネガティブな経験をしている
=足にも身体全体の感覚にも関心が薄れている
・身体を丸めて縮まっている
=「動くこと」よりとにかく安定したい
・足が宙ぶらりん
=役には立っていないが「邪魔な存在」ほどではない
・愛想がよい
=不快な経験でない限りは協力してくれそう
など、
戦略を立てる上で使えそうなパーツを組み合わせていきます。

アフォーダンスという考え方
「訓練」を提供する際、
課題を患者さんに理解してもらうにはいくつか手段がありますが、
私は主に以下の3つを使い分ける必要があると思っています。
①言葉を使って直接指示を与える
②模倣や指さしなど、非言語的な意志伝達
③アフォーダンス(注釈↓)
アフォーダンス(affordance)とは、「与える・提供する」という意味を持つ「afford」を元にした造語であり、「人や動物と物や環境との間に存在する関係性」を示す認知心理学における概念。(ジェームス・J・ギブソン)
環境や物は元から様々な使い方をアフォード(提供)しており、人や動物はその使い方を、説明なしでも過去の経験則から受け取ることができる。
例えば、
・ボタンは「押す」、レバーは「引く」
・ゴミ箱の蓋に開いた丸い穴は「カン」、平たい穴は「紙類」
・大きな風船は両手で挟むように持ち、取っ手の付いたコップは取っ手に合わせた手の形をつくる
・目の前の小さな障害物は跨いで歩けるが、大きな障害物は歩く方向を変えて避ける

これらのアクションは全て対象物が自分の行動をコントロールする、
認知理論で言う環境との相互作用です。
このような概念をアフォーダンスと呼び、
言葉を上手く使えない、模倣や指さしでの協力も難しい患者さんに狙った動きをさせる非常に重要な戦略の一つであると私は考えています。
アフォーダンスを応用する
話を戻します。
先ほどの患者さんは身体を丸めたいのではなく、
身体を丸める以外に安定する方法がない
と仮定すると、
丸める以外の身体が安定する方法を見つけるところからリハビリテーションはスタートするのが望ましい
と考えます。
そのためには、
関心の薄い部分の「感覚」が入ってくるべきなのですが、
やはり「宙ぶらりん」になっている「足」の存在が見過ごせません。
地に足をつけることは、
身体を安定させる原則であり、あらゆる動物が環境と相互作用するための基本なのです。
そこで、
「押す」という行動をアフォードする(引き起こす)環境を提供してみます。
できるだけ動きが分かりやすく、害が少なく、押した感覚が入ってきやすい刺激として
・風船
・バランスボール
・ウレタンマット
といった道具を選び、患者さんが動きやすい姿勢で手や足(特に足)を使ってもらいます。
押す方向
必要な力加減
体勢
を変えながら動いていただくと、
これまで封印していたお尻や背中の筋肉が働き出したようで、
ずっと丸まっていた患者さんの身長が伸びてきます。

それをご自身が言葉で表現する事はありませんが、
少しずつ身体の使い方を思い出してきているようです。
前回まで繰り返しお伝えしていますが、
身体を丸めている=力んでいる状態では感覚は入ってきません。
言葉が使えなくても「押す」という単純な課題をアフォードし、
自己と外界を繋げる「感覚」という要素を働かせることは、
身体を安定させる手段が丸めることから地に足をつけることへと変化させる戦略になってきているようです。
現時点では数回お会いした程度ですが、
回を重ねる毎に自分の足で何かを探索することが上手になっており、
「ちょっとでも自分の力で坐る」
という短期的な目標に大分近づいた(というか部分的にはクリアした)感があります。
まだまだ発展途上の段階ですので、どこまでリカバリーできるか?
介護ありきの生活は揺るがないですが、
自分の意思で座り方を直したり、
ベッドから離れるときに自分の足で少しは支えられるくらいの協力ができるかどうかは、介護する側にとって非常に大きな差です。
まとめ
久し振りに症例の話をしながら、セラピストにとって重要な視点について紹介しました。
言葉やジェスチャーが有効でない患者さんに対して、
アフォーダンスは環境が持つ動詞(押す・引く・持つ…)を利用して患者さんに何かしら行動を誘発する有効な手段になる可能性があります。
いわゆる重症者ほど、より低次なレベルで対象者の能力を確認したり誘導できると悩む時間も減ってくるかもしれませんね。
最近は専門的な内容が多くなって恐縮ですが、そろそろ脳科学シリーズもおしまいにしようと思います。
今日もここまでお読みいただき、本当にありがとうございました。
視覚と身体のセンサーを使い分けるには?
今日もアクセスいただき、本当にありがとうございます。
寅丸塾の管理人です。
できるだけ分かりやすい言葉で紹介していくシリーズでお送りしています。
前回、内部観察の重要性についてあれこれと語りました。
内部観察とは、患者さんが経験している世界について共有していく作業でした。
今日は、感覚情報と訓練についてもう少し掘り下げて考察していきます。
最後までおつきあいただけると幸いです…
感覚情報の分類
人間の感覚は、主に
・特殊感覚
・一般感覚
に分けられます。
特殊感覚とはいわゆる「五感」です。
視覚・聴覚・嗅覚・味覚・平衡覚のことです。
一般感覚は「体性感覚」と「内臓感覚」に分けられますが、
ここでは体性感覚をメインに考えていきます。
体性感覚とは、
・皮膚や表面のセンサーで感じ取る情報(硬い/柔らかい、冷たい/熱い、ツルツル/ザラザラ・・・など)
・筋肉や腱といった深部で感じ取る情報(関節がどのくらい動いたか、自分の手が今どこにあるか・・・など)
です。

冒頭から難しい単語を並べましたが…
何が言いたいかというと、
感覚にも色々あって、
人間は常にこれらの情報に晒されながらも、今必要な情報を選びながら動いている
ということです。
※入ってくる情報を全部処理していたら素早い反応はできない。優先すべき情報を取捨選択する必要がある。
例えば、
街中を歩く時は足元よりも周囲の人の流れや目標物などに注意を向けます。
一方で、ぬかるんだ山道を歩く時は、周囲よりも一歩一歩感触を確かめるように自分の足と地面に注意を向けます。
脳卒中片麻痺患者さんの歩き方は、地面の形状にかかわらず基本的に後者寄りであることが圧倒的に多いです。
そして健常者と違う点は、
筋肉のセンサーで足の位置や荷重感覚を確かめているというよりも
「地面を目で見て足がどこにあるかを確かめている」点です。
つまり、
足から得る体性感覚よりも、視覚への依存が強いことになります。

感覚の消去とは
これまで何度か繰り返してきましたが、
片麻痺患者さんは不安定な身体を何とか制御するために、「力む」という戦略を選択しがちです。
※力むと身体は固まって安定が増す代わりに、感覚が入ってこないという状態になります。
ですので、
今必要な情報は視覚なのか、聴覚なのか、体性感覚なのか
という使い分けが上手でありません。
結果、
本能的に目で見た情報を最も信頼し、それ以外は淘汰する
わけです。
それが繰り返されると、
「大して役に立っていない足の感覚に注意する必要はない」
「足の関節を全て動かないようにしてセンサー自体をoffにしよう」
と脳が都合のいい方法を学習した結果、
足を着いても足からは何も情報が入ってこなくなる、
すなわち「感覚の消去」が成立します。
視覚と体性感覚を一致させる
認知運動療法において、
患者さんのパフォーマンスを高めるために必要不可欠な視点は視覚と体性感覚の情報に整合性を持たせることです。
難しい表現をしてしまいましたが、平たく言うと目で見たことと足で感じたことがズレないようにする作業です。
足を地面に着いたとき、
足の場所は目で確認できることですが、
足の裏には床の感覚が入ってきますし、
体重を支える必要があるため足の裏には床を押すような筋肉のセンサーが働きます。
ただし、
そのセンサーは足の裏だけではなく骨盤・股関節から膝を介して足元につながります。
つまり、
「足を着いた場所」
と
「足の裏が床に密着する感覚」
と
「股関節が伸びる感覚」
は、
体重を支えるという目的において一致していないといけません。
したがって、
下を見ながら「力任せ」に歩くような患者さんに対して、セラピストは股関節の動きと足が床に沈む感覚がリンクしているかを確認しなければなりません。
これは私が病院にいた頃よくやっていた課題です↓

患者さんの両足をスポンジに乗せ、ゆっくりと沈ませたとき、
①「どちらの足が沈んだか?」
②「沈む動きはどの関節の動きに感じたか?」
③「どのスポンジ(何種類か用意してある)が沈みやすく感じたか?」
④「右と左のスポンジを入れ替えるとどんな感じになるだろうか?」
などなど・・・
これらの問われた質問に対して、患者さんは
①動きの有無や沈んだ感覚をざっくり左右比較する
②片方の足の中でも関節の違いを区別する
③沈みやすく感じる=筋肉とセンサーを同時に働かせる
④「このくらいの感覚になるはずだ」と予測する
というふうに、動きと感覚をリンクさせる必要があります。
上手くスポンジを踏めない患者さんにはセラピストが動きを介助して感覚を入れることを優先していきます。
区別がつきやすくなると、
自分の力をコントロールして動かす割合を増やしたり、
動く前に感覚を予測してから動いた後、どのくらいズレがあったか、
など難易度を調整していきます。
「難易度」とは、
患者さん一人では解決しにくい課題だがセラピストがヒントを与えたり誘導することで知覚できるものが望ましいと言います。
これを「最近接領域」といいます。
例えば、
「麻痺側の踵(かかと)がスポンジに沈む」
という感覚がセラピストに足を動かしてもらえば「分かる」のに、自分でやろうとするとつま先だけが沈み踵が浮いてしまうという問題が残る場合、
その患者さんは踵が沈んでいくためには「足の付け根」が伸びていくような動きが必要なことを理解していない可能性があります。
そこで、踵がスポンジに沈み込むためには
「今からあなたのかかとがスポンジに沈む動きを私が手伝いますから、股関節の動きに注意してくださいね、せーの・・・」
といった具合に
「股関節を伸ばす動きが踵に伝わってスポンジに沈みこむ」
ことを理解させ、最終的には
「歩く時に股関節から踵に力を伝えて床反力という感覚を得る」
ことへとつながっていきます。
実際にはかなり細かいやりとりをしながら患者さんの世界を広げていくのですが、
ブログという性質上このくらいの紹介とさせていただきます。
まとめ
患者さんは身体のバランスが崩れ自分の感覚があてにならないため、
分かりやすい「視覚」に依存した動きが強化されていきます。
視覚が強化されると、それ以外の情報は消去され、不必要な感覚が入ってこないようにするために身体はどんどん固まっていきます。
そこで、体性感覚というセンサーをしっかり働かせ、目で見る世界と身体の感覚を一致させるような課題としてスポンジを用いた認知課題をご紹介しました。
必要に応じて身体の感覚に注意が向けられる
ということは、それだけ汎用性のある動きができるという意味です。
患者さんは自律した生活を送りたいのであって、
「トイレ動作」「着替え動作」
を丸覚えしたい訳ではありません。
・行為そのものを反復的に学習させる
・行為につながる身体操作の基本を学習させる
どちらも引き出しとして持っておけば、質の高いリハビリテーションにつながると私は確信しています。
内容が内容ですので、どうしても難しくなってしまいましたが・・・
ここまでお読みいただき、本当にありがとうございました。
外から見た世界、中から見た世界
今日もアクセスいただき、本当にありがとうございます。
寅丸塾の管理人です。
最近は、セミナーの主なテーマにもなっている「運動学習」についての考察を記事にしております。
リハビリテーションにおいて、
患者さんに何かを学んでもらう
という視点は常に持っていかなければなりません。
前回、運動学習に必要な
「感覚」と「予測」
という視点で記事にしました。
今日は、もう少し専門的な内容に触れていきます。
(できるだけ分かりやすい表現で紹介していきます)
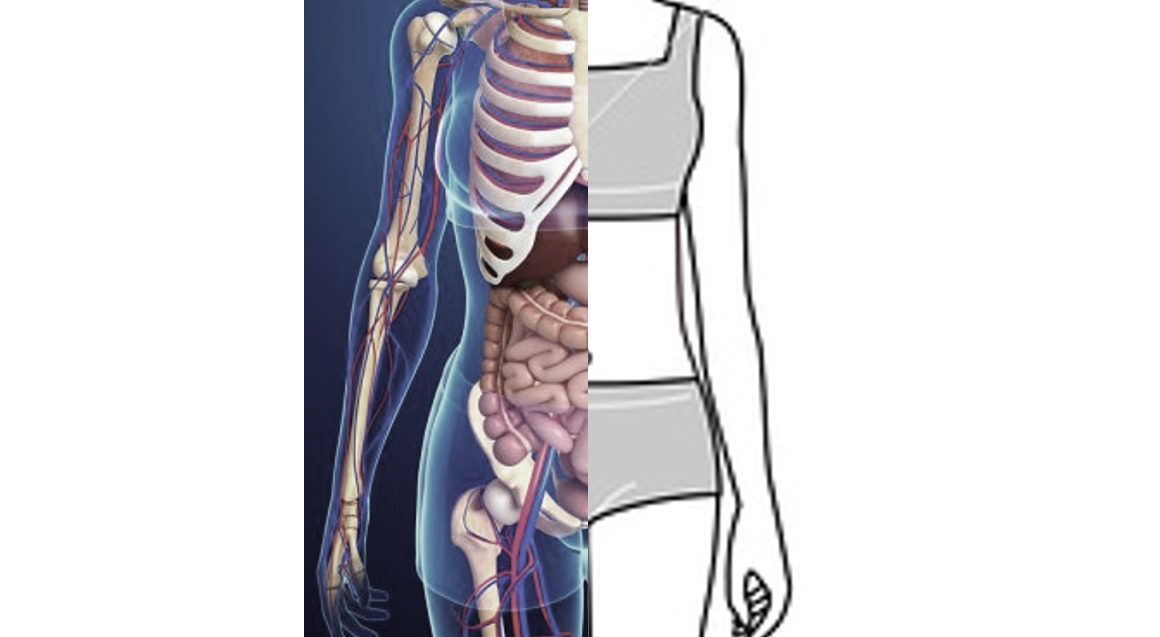
数字には表せないもの
人が人の問題を評価するとき、こと西洋医学においては「正常値」という基準があり、
そこからどれだけ逸脱しているか
という見方をするのが常識です。
リハビリテーションの世界でも、
患者さんを評価する際は一般的に「数字」を大事にします。
・関節の動かせる角度
・筋力の程度
・麻痺の程度
・感覚障害の程度
・手足の太さ、長さ
・知的な水準、高次脳機能
・日常生活自立度
など。
これらは全て、表に数字を書き込めば評価したことになる内容です。
リハドクターも、基本こういった数字を見て
「よくなった」「まだまだだ」
的な判断をしますので、
病院では基本的にこれらを把握することがほぼ必須となります。
一方、
どうやっても数字には表せないものがあります。
それは、
患者さんの訴え
です。
当り前のことかも知れませんが、
患者さんの「困っていること」や「これからどうなりたいか」という部分を訊かずに訓練をすることなどあり得ません。
学生でもそれくらいは把握しています。
ですが、
患者さんの「経験している世界」について、
セラピストは理解する努力を怠っている傾向が強い。
例えば、
片麻痺患者さんの多くは、歩く時に踵(かかと)を浮かしてつま先だけで体重を支えながら歩こうとする場面がよくみられます。
専門的には「尖足(せんそく)」と呼ばれる現象ですが、
何故つま先だけで歩こうとするのか?
「数字」の範疇で問題を考えると、
・ふくらはぎの筋肉が緊張していて足首の動きが〇度しか動かない
・麻痺の程度が〇点なので足元までコントロールできない
訓練は、
・ふくらはぎの筋肉を伸ばそう
・しっかり動かして麻痺の点数を上げよう
・必要なら装具を用いて矯正しよう
的な発想が生まれます。

では、
患者さんの「経験している世界」をベースに同じ問題を考えるとどうなるか?
・身体が不安定なせいで歩くこと自体が怖い
・坐っていればかかとは床に着くし「存在感」もあるが、立つと力任せになってしまい足元の感覚を感じる余裕がない
・足がどこにあるのかわからない
このような経験を患者さんがしているとしたら、
訓練はもっと繊細な作業になる必要があります。
つまり、
かかとの感覚は「ある」のに歩くと「無くなる」のは、
前回のテーマであった「力任せになって感覚が入ってこない状態」ですし、
そもそも患者さんは、
片方の手足だけが動かない状態というよりも姿勢制御の問題を抱えていますので、
高いバランス能力の必要な「歩行」という課題は実は「恐怖」との戦いです。
姿勢制御についての記事はコチラ↓
したがって、
「患者さんがかかとを床につけて歩ける」
という目標に対して、
・もっと前(起きる、坐る・・・)の段階での動きはどうか?
・どのような動きなら患者さんは怖さや力みを感じることがなくなるのか?
・かかとに体重がかかるという感覚を得るためには足の付け根から力を伝える必要があることを教えないといけない
など、様々な可能性を考えていく必要が出てきます。
外部観察と内部観察のバランス
このように、
患者さんの感じている世界を分析し共有していく作業を、
内部観察
と呼びます。
それに対して、数字ありきの評価を外部観察と呼びます。
セラピストは、
セラピスト以外の人と情報交換をする際は外部観察中心で話をして良いのですが、
セラピスト同士や患者さんと情報共有する際は、(外部観察を踏まえて上で)特に内部観察にウェイトを置いてディスカッションや治療を進めることが重要じゃないか
と私は感じています。
しかし、
内部観察を進めていくためには
患者さんの経験している世界を問うスキル(=質問力)
や、
上手く喋れない方の場合は見えないものを察するスキル(=洞察力)
が必須になります。
なお、
そこそこ長い病院勤務の中で、この思考が共有できた仲間は数人しかいませんでした。
臨床家にとって最優先事項は結果を出すことですので、
あくまでも1つの考え方に過ぎません。
しかし結果を出すには最低限知っておかなければならない知識があることも事実です。
急性期(発症してすぐ~医療的処置の必要が無くなる期間)メインの病院では、
患者さんは長くとも2ヶ月程度で目の前からいなくなります(=リハビリ転院)。
その間、患者さんの自然回復に伴って何かしらの「点数」を上げること自体は割と難しくありません。
なので、
結果を出すこと=少しでも点数を上げること
と大部分のセラピストが勘違いしています。
(上げられる部分は上げてよいことには異論ありません)
ただ、目先の点数に拘った結果、
「力任せの動きや感覚が入ってこないような動き方」
を学習してしまうために、
「その後の人生全てにおいて力任せで動かないといけない」
などという悲惨なことになりかねない。
特に急性期の病院にいるセラピストは、
自分の選んだ戦略が数字ではなく患者さんにとって適切な課題であるかどうか、
患者さんの人生の質を高めることにつながるものであるか、
よく考える必要があります。
私の場合、
・内部観察においては認知理論
・外部観察においては筋膜や経絡
を用いて現在のスタンスを確立しておりますが、
それでも日々患者さんと向き合うことの難しさを感じております。
その中でも、
質的な変化をクライアント自身が感じてもらえた瞬間は私自身も非常に嬉しいですね。
そうやって悩んできたことを、今は少しずつ後輩達に伝えていく努力をしているところです。
今日の記事はここまでです。
少し専門的な話になりましたが、ここまでお読みいただきありがとうございました。
セラピストの仕事は運動学習である
今日もアクセスいただき本当にありがとうございます。
寅丸塾の管理人です。
冷え込んだり暖かくなったりと気候が落ち着かない中、気合いを入れてPCと向き合っています。
前回の記事では脳卒中患者さんの脳内で生じる問題について考えました。
前回の復習
前回の記事を簡単にまとめると、
脳はシステムとして機能しているため、どこかが損傷すると全体のバランスが崩れ上手く機能しなくなる
機能解離というメカニズムにより脳は働くことよりも回復モードに入るため、無理矢理働かせることは強い矛盾がある
このような視点で、問題の本質に目を向けて訓練を提供することがセラピストの有るべき姿ではないか、
と述べてみました。
今回は、訓練を提供するにあたって、どのような点に注意を向けるかを考察していきます。
運動学習とは
何かを新しく覚えるとき、我々は大抵努力を要します。
例えば、
自動車教習所で初めて車の運転をしたとき、
体中に力が入っていて、冷や汗をかきながらハンドルやアクセル、クラッチにトランスミッション…
と、バタバタ操作した覚えがあります。(あれは今思い出してもヒドイ運転だった・・・)
が、
段々と手順が分かってくると力は抜けていき、
スムーズで余裕のある運転技術(※当時としては)が身についてきました。

要するに、
最初は力を浪費しながらトライ&エラーを繰り返し、徐々に成熟していく訳ですね。
この一連のプロセスを「運動学習」と呼んでいます。
そして、
運動学習において非常に重要な脳の機能があります。
それは、
「感覚」
と
「予測」
です。
感覚と予測
運動学習という範疇で簡単に説明すると、
感覚=自分の身体に生じた変化を認識すること
予測=自分の身体が次にどう動くかを予期すること
です。
自動車運転のスキルで言うと(やたらとMT車用語が出てきますが)、
アクセルやクラッチをどれくらい踏んだら車がどのような反応をするか
という情報は足から入ってくる感覚から養われるし、
ギアがどこに入っているか、次にどのギアに入れるか
という情報は正に次の行動の予測です。
このような視点でリハビリテーションを考えてみます。
多くの患者さんは動くために強い力に頼る傾向にあり、
そのような場面では「感覚」が入ってきにくい。
また、
力任せに動くために「次はこうしよう」という「予測」ができていないという傾向にあります。
もう少し具体例を挙げてみます。
テーブルの上のコップを取るためには手を伸ばす必要がありますが、
「手を伸ばす」という感覚はどういうものか?

まず、
肩が適度に緊張して腕(上腕)が体幹から離れていきます。
次に、
肘がコップとの距離を調節して必要なだけ伸びていきます。
そして、
コップに近づくと手をコップの形に合うように広げていきます。
最後に、
手がコップにたどり着いたらコップが持てるだけの握力と肩の力で持ち上げる
というように、
コップを持つという一見シンプルな動きでも、
実はかなり細かい関節の使い分けを必要とします。
健常者であれば、
これを無意識に制御しており何の違和感もなく目的を達成することができます。
肩・肘・手…と、ちょっと意識してやってみると確かにそれぞれの場所の動きを感覚として感じることができるはずです。
しかし、
これが脳卒中患者さんや上肢の外傷後の患者さんになると、
「力を入れて動かすこと」に必死になり、
腕の感覚や動きの予測が立たない傾向にあります。
結果、
肩も肘も手も固まり、身体をのけぞらせながら手を引っ張り上げるような動きになってしまう
というのは、セラピストなら誰でも見たことのある光景ではないでしょうか。
したがって、
力任せになりやすい患者さんにセラピストがまず教えなければならないことは、
「肩を中心に腕が身体から離れる感覚」
「肘が伸びる感覚」
「手首がおきて親指と他の指が離れる感覚」
ではないでしょうか。
患者さんが「コップを持つ動きとはどういう感覚か」を理解すると、
がむしゃらに力を入れるということをせずに済みます。
そして、
肩/肘/手の中で、特に苦手な動きやコントロールしやすい動きに気付いてもらいます。
例えば、
指を伸ばす前には掌をコップに向ける必要があります。
しかし、
手首を曲げたまま、手の甲をコップに向けたまま指を伸ばす患者さんは意外と多く、
そのような場合は動きの順序が分かっていない=「予測が立たない」状態
と言えます。
そうやって、
患者さんが気付いていない動きの原則を学んでもらうことは根性でどうにかなるものではなく、
「効率よく動ける」という意味で非常に重要であると考えます。
もちろん、
動き方が分かったからといってすぐに解決するものではなく、
運転技術を磨くように根気よく「腕の感覚を磨く」というタスクを提供していかなければなりません。
しかし、
それは直接患者さんの身体に触れるセラピストにしかできない作業であり、患者さん自身の意欲や信頼関係次第で進歩していくものだと信じております。
まとめ
今回は運動学習について記事にしました。
・動きに重要な要素は「感覚」と「予測」である
・患者さんは力任せになりやすく、上記いずれの要素も欠落している可能性がある
・セラピストは患者さんに何を感じながら動くのが望ましいのかを明確に伝える必要がある
といった内容でした。
今日もここまでお読みいただき、本当にありがとうございました。
脳卒中を診る時に忘れてはならないメカニズム
今日もアクセスいただき、本当にありがとうございます。
寅丸塾の管理人です。
新年明けましておめでとうございます。
波乱の年末年始ですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
私はというと、家族で妻の実家にお邪魔しては子ども連中にいいように遊ばれました…
それはともかく、
今年も本業に支障が出ない程度に、横のつながりを広げていきたいと思っています。
脳はシステムとして機能している
少し前から、「脳卒中」についてのトピックスについて解説しております。
前回は、
脳卒中のリハビリで必要なスキルについて紹介しました。
今回は、脳卒中患者さんの「脳の中」について考えていきます。
脳卒中といっても様々な種類がありますが、
殆どの脳卒中に共通する問題は、
脳の血管が切れたり詰まったりすることで栄養不足による脳細胞の「壊死(えし)」です。
つまり、
運動や感覚の中枢を担う脳細胞の壊死が「麻痺」として表れるのですが…
臨床においては、
運動や感覚の中枢でない脳細胞の壊死でも「麻痺」は出現します。
病院時代はよく、画像所見(CTやMRI)上で
「この辺の出血なら麻痺はそんなにでないはずなのに・・・」
とか、
「この人梗塞は小さいのに動くのめっちゃ下手じゃね?」
みたいな会話が耳に入ってきました。
脳細胞には様々な役割分担があり、それらがシステムとして機能しています。

システムとして機能する
とは、
「どれか一つでも欠けると本来の機能が著しく制限される」
という意味であると理解しています。
パソコンで言うと、
どこかのコードが1本切れただけで画面が写らず仕事にならないようなものでしょうか。
つまり、
「ここは損傷しているけどここは無事だから、このくらいはできるはずだ」
というセラピスト側の思い込みは非常に危険です。
健康な状態を仮に「100」とすると、
損傷したエリアが「10」なら、
差し引いた残りの「90」は使えるだろう、
という考え方が、
「残存機能で日常生活の練習をしていけばその内できるようになる」
という戦略を強化してしまい、
本質的な問題である姿勢制御や随意運動という機能障害と向き合おうとしないことが、残念ながら現在のスタンダートです。
機能解離という現象
繰り返しになりますが、
脳卒中は脳の血管が破れたり詰まったりする事で生じる血流の問題です。
したがって、
発症後暫くは脳の中に血が溢れたり途絶えたりします。
脳に血が溢れると、脳自体を圧迫することで脳が腫れ、頭の内圧が高まった状態になりやすいため、そもそも頭が回りません。
しかし、
徐々に血が引いてくると内圧も低下してくるため、
急性期病院のリハビリテーションにおいて、多くの脳卒中患者さんの状態は日に日に変化します。
これは、あくまでも患者さんの持つ自然回復にすぎません。
ですが、
目に見えて患者さんの状態が良くなってくるものだからセラピスト自身が
「自分のおかげだ」
と勘違いし始めると、どんどん課題を要求していきます。
しかし、
ここで注意しなければならないことは
「システムが破綻した状態は続いている」
ということです。
つまり、
患者さんのコンディションは
100-10=90
ではなく、もっと低下した状態です。

上のように、
一部が損傷した状態になると上手く情報が処理できなくなります。
すると、
自動的に損傷した部位に負担をかけないように周辺の組織が仕事量をセーブして、全体の機能を抑制するように働きます。
つまり、
仕事よりも休息を優先し、自然治癒力を高めるモードに移行するわけです。
これを機能解離現象と呼んでいます。
したがって、
患者さんの自然回復を促すという意味においては、
あれこれと運動をさせ続けることは矛盾を来たします。
「動かすな」
と言っている訳ではありません。
運動学習を促す立場であれば、
・なぜ下手なのか?
・なぜ麻痺していない側の動きにもこんなに努力がいるのか?
・何から学ばせる必要があるのか?
を考えて、より戦略的なリハビリテーションを提供していくのが我々の仕事です。
※
なお、機能解離現象は発症後3ヶ月程度まで徐々に緩解しながら続きます。
これが、脳卒中の回復は概ね3ヶ月程度まで、と言われている根拠になります。
ただし、それ以降の回復については「運動学習」という要素が非常に重要になります。
それについてはまた後日、記事にします。
脳科学という学問は難解で敬遠されやすい分野ですが、
臨床につながる最低限の知識は専門家として絶対に必要です。
「私は脳のことは分からないです」
と平気で口にするセラピストをこれまで何人も見てきました。
脳が分からないセラピストに脳卒中患者さんの何が分かるのだろうか?
これをお読みになっている方で、身近な人でリハビリテーションを受けている方がいらっしゃったら、
納得して治療が受けられているのかもう一度よく確認してみてはいかがでしょうか?
最後に毒を吐いて締めくくりましたが、
今日もここまでお読みいただきありがとうございました。
脳卒中の機能回復について考える
今日もアクセスいただき、本当にありがとうございます。
寅丸塾の管理人です。
色々と大変だった2020年も、もうすぐ終わろうとしていますね。
最近は、講習内容の関係で、病院時代の脳卒中患者さんを診ていた頃のことをよく思い出すようになりました。
ので、今日も脳卒中とリハビリについての考察です。
姿勢制御を優先した訓練とは
前回、脳卒中のリハビリをしていく上で、
誰の目にも明らかな手足の麻痺よりも、姿勢制御の問題を考えていく方が重要だ
という話をしました。
簡単に復習しますと・・・
手足を動かすと、それに伴って必ず重心が移動します。
その際、重心が身体の外へ移動して倒れてしまわないように、無意識に姿勢のバランスをとっていますが、
殆どの脳卒中患者さんは、この無意識的なバランス能力が低下します。(程度の差は様々ですが)
その代償として、手足に力を入れたり全身を固めて動こうとするわけですね。
こういった動きを繰り返すことで、最低限の動きは獲得できますが、あくまでも「とにかく動ければいい」という方法論です。

この、
「一応動けてはいるけどこんなはずじゃなかった」
という学習をしてしまわないために、
「姿勢制御」
という視点で患者さんを診ていくことがセラピストには求められます。
では、どのようにすれば姿勢制御を獲得することができるのか?
患者さんの多くは麻痺した手足を動かすことに努力を要しますが、
麻痺していない側の動きも万全ではありません。
なぜなら、
右でも左でも手足を上げるときには身体が倒れないようにバランスを取らなければならないため、
多くの患者さんは重心が変化する事を無意識に避ける傾向にあります。
そして、
「力を入れて身体がブレないように動く」
ことを最優先に学習していきます。
しかし、
患者さんにとっては麻痺している側の手足の方が重要度が高いため、
そのこと自体に疑問を抱く方は少なく、
「麻痺してない側は問題ない」
という結論に患者さんもセラピストも誤解しやすくなります。
このとき、セラピストは
「麻痺してない手足を動かすときに患者さんはどのような感覚を優先しているのか」
という視点を持つことが重要になります。
臨床的にとても多い具体例を挙げてみましょう。
患者さんは何もせず椅子に座っているときは両方のお尻に体重が乗っているが、
麻痺してない右手を上げた瞬間に右のお尻にかかっていた体重が抜けてしまい、麻痺側に崩れてしまう。
その時に、患者さんはとにかく力を入れることに精一杯で、体重が抜けたお尻のことには無頓着だ。
といった、
患者さん自身が感じている世界について共有していく努力が必要になります。
これを、
専門的な表現で内部観察といいます。
このような問題は、臨床では日常茶飯事です。
もちろん、我々健常者はいちいち手を上げたときのお尻の感覚なんて気にもしません。
なぜなら、子どもの頃から学習してきた姿勢制御システムが正常に働き、オートマチックにコントロールしているから。
しかし、脳卒中によって身体の構造に変化が生じた患者さんにおいては、一度学習したシステムがリセットされます。
つまり、
オートマではなくマニュアルモードで制御しなければならなくなる。
そこで、
「お尻が浮かないように意識しながら手を上げてみましょう」
「麻痺してない側の感覚の変化にしっかり目を向けながら、ゆっくりと動きましょう」
といったように、
動くときに何に気をつけるのかを明確化することで、
力任せになりがちな患者さんの注意や感覚を操作して、力を使わなくても済むような動きの学習を進めていきます。
この工程をより細かく訓練に組み込んでいくことが、身体を固めずに姿勢制御を高めて病理を制御する
ということに繋がっていきます。
これは、
例えば車の運転を練習するとき、
はじめはガチガチに力が入っている
→手順や視点、フットワークを覚える
→徐々に自分の感覚を磨く
→流れるような動きを獲得する
ということからも、
あるスキルの成熟には「感覚が非常に重要」であることが分かります。
我々セラピストは人間の動きについて専門的な知識を持ってはいますが、
・運動には様々な感覚が伴うこと
・多くの患者さんはそれが上手く整理出来ていない可能性があること
・外から見るだけでなく、患者さんの感じている世界について共有すること
これらの視点がしばしば欠落しがちになります。
あくまでも一つの例として紹介させてもらいましたが、
「頑張らせ過ぎている」
と感じた時には一旦立ち止まって、
目の前の患者さんがどのような感覚を優先して動いているのかをしっかり考えてみることが、患者さんの今後の生活の質を左右していくかもしれません。
これらは、
という理論の中では核となる考え方ですので、
「興味はあるけど認知~は難しい」
と思っている方、詳しく話を聞いてみたい、
という方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。
今日もここまでお読みいただき、ありがとうございました。
よいお年を。
脳卒中のリハビリについて久し振りに向き合ってみた
今日もアクセスいただき、本当にありがとうございます。
先日から寅丸塾に新しい門下生が入り、何から指導していこうかと考えさせられる日々を過ごしております。
どこの町でも同じことが言えるでしょうが、いわゆる急性期病院で働くセラピストは日常的に脳血管障害(脳卒中)を抱えた患者と向き合っています。
新しく入門した彼も、そんな環境で働くセラピストの一人です。
今でこそ私は自由診療分野で価値を提供することにフォーカスしておりますが、
以前は彼と同じ立場で日々悩みながら臨床経験を積んでいました。

大きな組織の優先事項は足並みを揃えること
地域の中核病院に相当する組織は、人員もそれなりに多くなります。
一般的な感覚で病院の価値感をイメージすると、
「人が多い=信頼できる」
「優秀な人材がそろっている」
「最新の機器で治療をしてくれる」
という、日本人が陥りやすい根拠のない安心感が生まれます。
もちろん口コミや「〇〇疾患に強い医者がいる」
という評判も重要だと思いますが、
こと「リハビリ」に関しては
「あそこの病院にはいい先生がいる」
というような話は聞いたことがありません。
何が言いたいかと言うと、
直接患者さんの身体に触れるセラピストの仕事は一般の方には価値が伝わりにくく、
「良いリハビリを受けられたかどうか」
は、主治医よりも担当したセラピストの技量や対応力次第
ということです。
したがって、
セラピストは日々自分の技術を磨き少しでも多くの価値を提供できるようになることが求められます。
しかし・・・
私がこれまで実際に見てきた病院業務では、
セラピスト個人が高いスキルを持つことは
「他の者に再現出来ないような技術を使われると迷惑がかかる」
という理由から否定的に考えられる傾向にあります。
「迷惑」とは誰に対してでしょうか?
セラピスト同士の力量に差が生じることは、そのまま患者さんへのサービスの質の差となり、
「あの先生はこうしてくれたのに」
という患者さんからの評価につながる訳です。
つまり、
スキルの水準を高い所に持っていくことよりも、低い水準に合わせないと患者さんに不公平でしょ?
といった、患者さんを守っているようで実は自分達が成長したくないだけ(もしくはリーダー役の人間の狭い価値感に支配されている)という思考が多くの組織で蔓延しています。
もちろん、
組織である以上ある程度足並みを揃える必要性があることは過去10年以上の経験から十分に理解しております。
しかし、職人であれば経験値によって力量が異なるのが当然です。
方向性やルールは共有しつつも、
「あの先生もいいけどこの先生は少し違った見方で診てくれて面白い」
と感じてもらえる環境を作る責任が我々にはあります。
そのような環境づくりができないのは、
診療報酬という制度に我々が胡座をかいてきたからに他ならないのですが。
パラダイムをシフトする
話が大幅に脱線しそうなので、とりあえず本題に戻ります。(診療報酬についてはまた記事にしてみます)
結果を出せるようになりたいという彼も、
組織の方向性に不満を抱きながらも自分自身に実力がないせいで何も変えることができない
そんな自分に最も不満を抱いているように私には映りました。
色々と話を聴いてみて、まずは基礎知識をつけることから・・・
と講義をしてみたところ、色々と気づきや学びが得られたようでとても満足してくれたようです。
そして、日常業務に生かす上で疑問はあるか?
と尋ねてみたところ、
自分の病院では脳卒中患者さんの訓練はとにかく立たせること、歩かせることが当り前になっているが、他にどんな課題があるか?
という質問をいただきました。
脳卒中といっても診断名も障害の程度も様々ですので個別性を重視するのは当然ですが、
ここでは典型的な片麻痺の患者さんを例に挙げてみます。

病院で遭遇する多くの脳卒中患者さんは、このように片側の手足が上手く使えません。
そこで、
上手く使えるようになるためには手足を動かす練習をする
つまり、
・手なら物を掴む練習
・足なら歩く練習
を繰り返すというのが、我々が学校で習った訓練の方向性です。
???
その程度なの?
わざわざ学校行ってお金払ってまで教わった内容が
「誰でも思いつくレベルの訓練」
なら、
「セラピストなんて誰がやっても一緒じゃねーか」
という声が聞こえてきそうです。
実際に脳卒中の後遺症に悩んでいる方は多いですし、直接関わったことがある方ならイメージが出来ると思いますが、
片手片足が使えなくても自分ならもうちょっと上手に動く自信がある
と、自分も思ったことがあります。
しかし、
現実にはものすごく下手で身体の柔らかさが殆どなく、介護がないと生活できない人が大多数です。
これは、
手足の動き以前に体幹の機能が破綻し自分の身体を支えること自体が困難になっているため、身体を昆虫のように固めることでどうにか安定させる
という、動物としての防衛本能が働いた結果であると私は理解しています。
つまり、
目に見える手足の障害よりも患者自身の軸をつくる
ことに優先順位をおく勇気がセラピストには必要です。
これは私たちが赤ちゃんの頃、どういう順番で動きを獲得してきたかを考えると分かりやすいと思います。

乳児はまず重力に逆らって頚を起こすことから学び、
腕を動かしやすい姿勢が作れてから玩具を扱います。
徐々に重心(骨盤)を高い位置に持っていき、1年経ってようやく立ちあがり歩き始める訳です。
この順番をすっ飛ばしていきなり歩かそうとすると、
原始的な反射(全身に力が入る・背中を反らせて嫌がる、など)が起こります。
それを繰り返すと、身体を固めて何とか立位に対応しようとしますが全身に力が入った状態は抜けず、結果的に身体の自由度が非常に制限されることになります。
したがって、
目の前の患者さんの動けるレベルに合わせた課題を緻密に計算していくことがセラピストの最重要課題である
ということです。
この考え方があるのとないのでは、結果に天と地ほどの差が生まれることがお分かりになるでしょうか。(重度の障害を抱えた方に対しては出来ることも限られてきますが・・・)
具体的な話に戻すと、
訓練室に連れてきて無理矢理歩かせるよりも、
自分のベッドの上で自力で起き上がるための身体の使い方をゆっくり学んでもらう方が100倍価値があります(あくまでも経験上)。
ただし、
患者本人は「歩かせてもらえた」という経験をポジティブに捉える傾向があることも事実です。
ですので、訓練のモチベーションを高めるために現状把握という意味で歩いてもらうことには異論ありません。
肝心なのはセラピストが今何を優先して目の前の患者と向き合うか。
そのような話を、
久し振りにアウトプットすることで自分も再学習させていただきました。
病院で働くセラピスト一人一人が、しっかりと自分の現状と目標を把握出来るようになればリハビリテーションの質も高まってくるのでしょうが・・・
尾道・三原・福山圏内で、一緒に学んでみたいという方がおられましたら、お気軽にコメントください。
今日もここまでお読みいただきありがとうございました。


